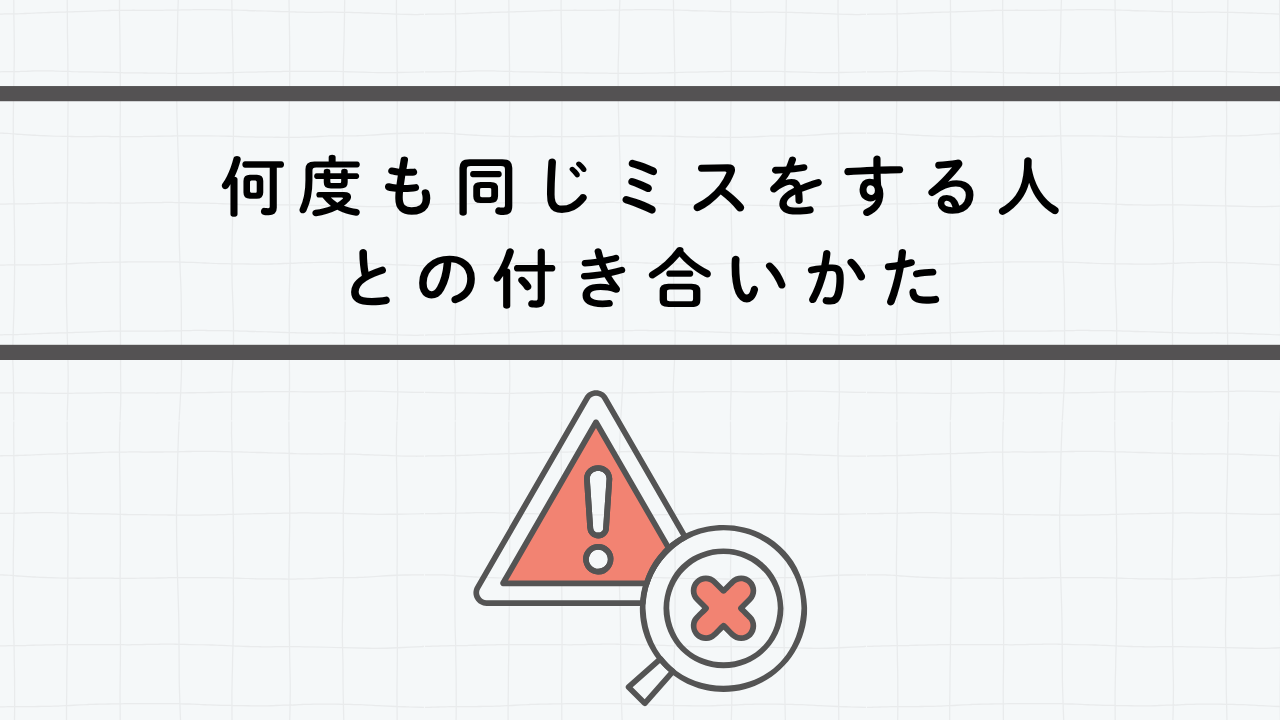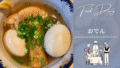教えても教えても、同じミスをする人。
教えた立場としては、自分がミスをした時とは違うがっかりというか、歯痒さというか、そして自分の教え方が悪かったとかと不安になったり、ストレスを感じる場面かと思います。
私は、4月から特性があるっぽい新人の教育係をやっています。毎日、隣で仕事を教えていますが、仕事上のコミュニケーションがうまく取れず、普通では考えられないエラーが続き、それに耐える日々を送っています。
ミスを繰り返す人はいる
世の中には、あなたがどんなに丁寧に、熱心に仕事を教えても身につかない人もいます。まずはこのことを認識することが自分への救いとなります。
教育係に任命される人は、きちっと仕事をしてきた人が多く、他人のミスについても背負いがちです。自分の心のために、世の中にはミスを繰り返す人がいて、それは自分の教え方のせいではないと思うようにしましょう。
その認識の上で、対策をリストアップしておいて、それを超えてきたら自分のせいではないと心の線をひきましょう。
3回までは教え方を工夫して付き合う
1回目はベースを教えてから作業へ
初めて仕事を教える場合は、知識のベース作りから始めます。なんのためにやるのか、いつまでにやるのか、などその仕事を理解するための知識を説明しましょう。
おそらくミスを繰り返す人はここで脱落しています。メモを取ることができなかったり、理解していない様子であれば、紙に書いたものを渡すなど工夫が必要になります。
ベースのあとに具体的な作業を教えていきます。マニュアルがあれば参照しながらメモを取らせ、やってみせるのが良いと思います。
可能であれば、その流れのまま作業をさせられるとなお良いでしょう。見聞きするのと、実際にやってみるのとは記憶の定着が違います。
2回目は1回目の補足説明
1回では習得できなかった場合、2回目は1回目の説明に不足があった可能性があるので、不足を補うために理解度をすりあわせます。
本人に具体的にどこがわからなかったのか説明してもらいます。厳しいようですが、1度教わったのですから、知識を補完するための作業は主体的でなくてはなりません。
おそらくミスを繰り返す人は、自分の理解度を説明することができません。その場合はキャパオーバーなので、その仕事の作業の一部を任せるなど、タスクの分散が必要です。
3回目は最終通告、それ以降はイレギュラーのみ
2回目のすりあわせを行ってなおミスをする場合は、最終通告をします。気持ちが弛んでいるのかもしれません。
ただ単に同じミスを2度繰り返した場合と、イレギュラーがあった場合や理解度が進んだ上での発展的なミスは別に捉えましょう。
3回目の教え方も、基本的には2回目と同じです。主体的に知識の補完を行ってもらいます。
ミスを繰り返す人に対しては、分散をしたタスクができるようになるかを観察します。難しければさらにタスクを分けますが、どうにもならない場合は、努力してもできない作業内容なので上司に報告して諦めましょう。
怠けてる人は案外いない
ミスを繰り返されると、「怠けている」「やる気がない」「仕事を舐めている」と思いがちです。
ただ、他人に怒られてまでミスをしたい人っているのでしょうか?
あなたを困らせている人は、怠けているのではなく、仕事の身につけ方がわからなかったり、どうしても理解することができなかったり、本人も説明することができない事情があるのかもしれません。
怒りにとらわれてしまうと、教える側、教わる側どちらにも良いことはありません。
心を壊されないように、3回までのルールで線引きしていきましょう。
茄子の肉味噌炒め

今日は茄子が安かったので、肉味噌炒めにしました。ホカホカのご飯に乗せて食べました。